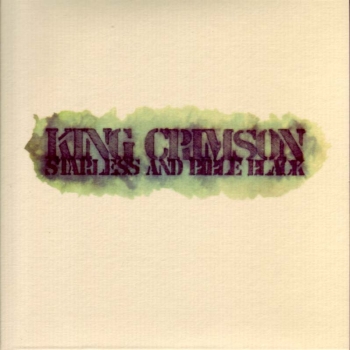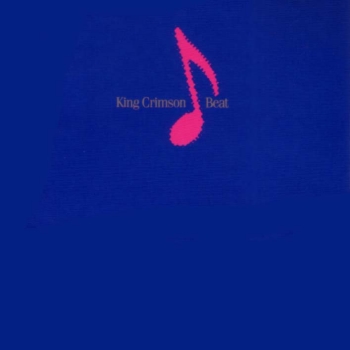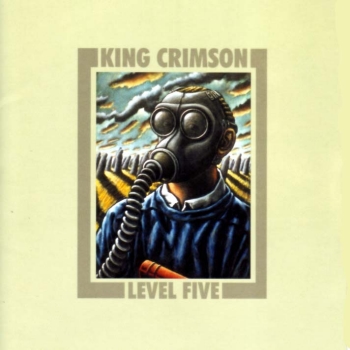【クリムゾン・キングの宮殿】
01. 21st Century Schizoid Man (including Mirrors)/21世紀の精神異常者
02. I Talk to the Wind/風に語りて
03. Epitaph (including March for No Reason,Tomorrow and Tomorrow)/墓碑銘(理由なき行進・明日又明日)
04. Moonchild (including The Dream,The Illusion)
05. The Court of the Crimson King (including The Return of the Fire Witch,The Dance of the Puppets)/クリムゾン・キングの宮殿(帰って来た魔女・あやつり人形の踊り)
Crimsonを扱う各種のHPを覗いてみると、『宮殿』に打ちのめされた人は多く、しかも不思議とその年齢は中学生ぐらいであるようだが、あるいはその年代あたりから本当の意味で“音楽”というものの力を理解するようになるのかも知れない。そして、成長してから聴き返してみて、このアルバムが一向に色褪せていないことに驚き、一方で10代前半ですでにこうした“音”を聴いていた自分に驚く、というのもまた共通する要素であるようだ。
管楽器の積極的な多用と、メロトロンの叙情性がこのアルバムの音作りの特徴ではあるが、それに加えて、すでに独自の領域を築き上げていて、このような叩き方をするドラマーは他にはいないMichael Gilesをはじめとして、デビュー作にも関わらず個々のメンバーの超絶技巧が冴え渡る。1曲目の21st Century Schizoid Manは、不協和音ぎりぎりの構成と、中間部8分の6拍子の見事なユニゾンプレイで歴史に残る名曲。Epitaph及び表題曲The Court of the Crimson Kingでは、メロトロンがデカダンスな叙情性の彩りを添えるのに貢献している。また、意外と指摘されていないことだが、Robert Frippはこの初期Crimsonの2作品においてはエレクトリック・ギターよりもアコースティック・ギターを使う比重が高く、それもまたこのアルバムの特異性だと言えるだろう。
2009.08.23追記 現時点で21st Century Schizoid Manの邦題は“21世紀のスキッツォイド・マン”となっているが、何故「精神異常」を自主規制語とするのか理解不能である。そもそもschizoidの正確な訳語はかつては「精神分裂病」であり、今日それが「統合失調症」と訳し換えられているのだが、「分裂」=「統合の失調」ではないのだろうか? だとすればこうした語の置き換えによって、一体何が排除されたのであろうか? さっぱり意味不明であり、仮にその内幕が分かったとしても到底納得できないと思われる。それゆえここでは本来の邦題を敢えて挙げておく。